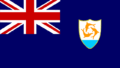もうすぐ新年!年越しの準備はできていますか?多くの方が新年の始まりに初詣
出典:「初詣はお寺と神社どちらに行く?参拝やマナーの違いとは|村松虚空蔵尊だより⧉」|taraku.or.jp
https://www.taraku.or.jp/blog/hatsumode/hatsumode-shrine-temple/
へ出かけるかと思いますが、いつ初詣に行くのが正解か、実は大晦日から参拝する「二年参り」という習慣があるのをご存知でしょうか?なんとなく行っている初詣や二年参りの意味を知ることで、あなたの年越し参拝はより深く、有意義なものになるでしょう。
この記事では、年越しに神社へ行く「二年参り」について徹底解説します。二年参りの由来、意味、ご利益、そして知っておきたい参拝マナーまで詳しくご紹介。この記事を読めば、あなたが年越し参拝をより深く理解し、清々しい新年を迎えるためのヒントが見つかるはずです。
二年参りとは?基本情報と初詣との違い
年越しの神社参拝として知られる「二年参り」。まずはその基本的な意味と、一般的な初詣との違いについて見ていきましょう。
二年参りの定義
二年参りとは、大晦日から元旦にかけて、二つの神社を参拝する習慣を指します。具体的には、大晦日の夜に神社へ行き、一年の感謝を伝え、日付が変わる前または変わった直後に再度参拝することで、新しい年への祈願を行います。また、調整さんの記事によると、日付変更付近に一度だけ参拝を済ませることも「二年参り」と呼ぶ場合があるようです。
初詣との違い
初詣は、新年の始まりを祝い、その年一年の平穏を祈願するために神社や寺社に参拝する行事です。一方、二年参りは年越しの瞬間を神社で迎え、過ぎゆく年への感謝と、来る年への祈願を同時に行う点に特徴があります。村松虚空蔵尊だよりによると、二年参りの由来は、古来日本で行われていた「年籠り」という行事にあるとされ、この年籠りが大晦日の「除夜詣
出典:「「大晦日」「除夜の鐘」「初詣」の意味・由来とは?知っておきたい年末年始の文化|【公式】樹木葬なら松戸家⧉」|【公式】樹木葬なら松戸家
https://mazdoya.co.jp/jyumokusou_flowerge/column/column133/
」と元旦の「元日詣
出典:「「初詣の意味と由来~日本の伝統文化を知ろう~」|大谷義則⧉」|note.com
https://note.com/sai_chat_gpt/n/na6e40715ea25
」に分かれ、現在の初詣の形になったとされています。
二年参りの一般的な流れ
二年参りでは、まず大晦日の夜に神社へ行き、その年一年の無事に対する感謝を伝えます。そして、日付が変わる前後に再度参拝し、新しい年の幸せを祈願します。地域や個人の考え方によっては、大晦日から元旦にかけて一回の参拝で済ませることもありますし、二年参りの後、元旦に改めて初詣を行う人もいます。
「年越しに神社に行くのは普通?」Yahoo!知恵袋の事例
Yahoo!知恵袋には「初詣に神社に行って年越しって普通ですか? 12月31日の夜中に行って、そこで年を越すってことです」という質問が寄せられています。これに対し、ある回答者は「普通というかどうかは分かりませんけど、『流行』の一つですね」と答えています。また、かつては公共交通機関の終夜運転が始まったことをきっかけに、年越しで参拝する「二年参り」が流行し、今では全国的に宵越し(年越し)で参拝する人もノーマルなことになったと説明されています。このことからも、年越しに神社へ行くことは、現代では広く受け入れられている習慣であることがわかります。
二年参りの由来:なぜ年越しに神社へ行くのか?
年越しに神社へ行く習慣である「二年参り」の意味や由来は、古くからの日本の信仰に根ざしています。
「年籠り」の習慣から派生
二年参りや初詣の由来は、古来の「年籠り(としごもり)」という習慣にあります。村松虚空蔵尊だよりや東洋経済オンラインの記事によると、これはかつて家長が大晦日の夜から元旦の朝にかけて、家族の守り神である氏神様の神社に籠もり、前年一年の感謝と新しい年の祈願を行う習慣でした。この「年籠り」が、時代の変化とともに二つの行事に分かれていきました。
「除夜詣」と「元日詣」への分化
年籠りは、大晦日に一年の感謝を伝える「除夜詣」と、新年に年の平穏を祈願する「元日詣」に分かれました。調整さんの記事でも、この分化について触れられています。この二つの参拝を続けて行うのが、現代の「二年参り」の原型と言えるでしょう。
明治時代以降の初詣の普及
現代の「初詣」の形が定着したのは、実は明治時代以降のことです。東洋経済オンラインの記事によれば、本来は家の長が代表で氏神様に参拝するものでしたが、鉄道の普及などにより、より遠くの有名な寺社に参拝することが流行しました。二年参りは、こうした歴史の中で、昔ながらの年越し参拝の習慣を今に伝える貴重な文化となっています。
二年参りのご利益:どんな願いが叶う?
年越しに神社へ行く「二年参り」には、どのようなご利益があるのでしょうか。その意味と、具体的なご利益についてご紹介します。
一年の締めくくりと始まりを神社で迎える意味
年越しという特別な時間を神社で迎えることは、単なる参拝以上の深い意味を持ちます。過ぎ去る年の厄を払い清め、新たな気持ちで新年を迎えることができます。神聖な空間で参拝することで、心身を清め、神様の清らかな力を得て、清々しいスタートを切ることができるでしょう。
ご利益の種類
二年参りで得られるご利益は多岐にわたります。一般的には、家内安全、健康祈願、商売繁盛、恋愛成就、学業成就などが挙げられます。自身の願い事に合わせて参拝する神社を選び、心を込めて祈願することが大切です。
年末年始は神様のパワーが強い時期
村松虚空蔵尊だよりによると、年末、特に冬至(12月22日頃)は、日本の古い暦で新しい年の始まりとされ、仏様や神様のパワーが強まる時期と考えられています。この時期に参拝することで、神様の強い力を受け、大きなご利益を得やすいと言われています。年越し参拝は、まさにこの神聖なパワーが高まる絶好のタイミングなのです。
ANA Japan Travel Plannerからの情報
ANAのJapan Travel Plannerでは、初詣について「一年の健康や幸せを祈願する伝統行事」と紹介されています。また、お守り
出典:「お守りの種類や意味・起源について総まとめ | 大阪・和歌山のおでかけ情報otent(おてんと)⧉」|otent-nankai.jp
https://otent-nankai.jp/category/topic/221221_omamori-type_844
、御朱印、絵馬などを活用して参拝をより楽しむことができると推奨されています。二年参りでも同様に、これらの縁起物を活用することで、ご利益を一層高めることができるでしょう。
年末詣のメリット
出典:「年末詣とは年末にお参りして感謝を伝えること!由来や参拝時のポイントなどを解説 | Oggi.jp⧉」|Oggi.jp
https://oggi.jp/6606746
「二年参り」の一環として、大晦日以前に参拝する「年末詣」という習慣もあります。村松虚空蔵尊だよりによると、年末詣は初詣に比べて比較的空いており、落ち着いた雰囲気でゆっくりと参拝できるというメリットがあります。また、新年に向けて神社の境内も清められているため、清々しい気持ちで神様に感謝の気持ちを伝えることができるでしょう。
二年参りの参拝マナー:知っておきたい作法と注意点
年越しに神社へ行く「二年参り」をより有意義にするためには、適切な参拝マナーを知っておくことが重要です。
参拝前の準備
- 服装:大晦日から元旦にかけての夜間は非常に冷え込みます。防寒対策をしっかり行い、温かい服装で参拝しましょう。
- 持ち物:お賽銭はもちろん、お守りや御朱印をいただく予定がある場合は御朱印帳を忘れないようにしましょう。
- 情報確認:参拝する神社の場所、開閉時間、混雑状況、公共交通機関の運行状況(終夜運転の有無など)を事前に確認しておくことをおすすめします。
参拝の流れ
ANAのJapan Travel Plannerでも紹介されているように、一般的な神社参拝のマナーを守ることが大切です。
- 鳥居をくぐる際の礼:神社の入り口にある鳥居は神域との境を示すものです。一礼してからくぐりましょう。
- 手水舎での清め方:

出典:「手水舎で行う手水のやり方は?行う理由やマナーもご紹介|村松虚空蔵尊だより⧉」|taraku.or.jp
https://www.taraku.or.jp/blog/hatsumode/how-wash-your-hands-chozuya/
参拝前に手水舎で手と口を清めます。
- 参拝方法:お賽銭を入れ、「二礼二拍手一礼」で心を込めて祈願します。
参拝時の注意点
- 敬虔な気持ちで:神聖な場所であることを意識し、静かに敬虔な気持ちで参拝しましょう。
- 迷惑行為の禁止:他の参拝者の迷惑になるような行為は慎みましょう。
- 写真撮影のマナー:写真撮影が許可されている場所でも、フラッシュの使用や神様に向かっての撮影など、マナーに配慮しましょう。
二年参りにおすすめの過ごし方
年越しに神社へ行く「二年参り」は、日本の習慣や文化を深く体験できる素晴らしい機会です。ぜひ、自分に合った過ごし方を見つけて、特別な新年を迎えましょう。
大晦日の過ごし方
参拝に行く前に、日本の伝統的な大晦日の過ごし方を楽しむのも良いでしょう。家族や友人と一緒に除夜の鐘を聞きに行ったり、年越しそばを食べたり、紅白歌合戦を見るなど、それぞれの家での年越しの習慣を楽しむことで、より一層二年参りへの期待感が高まります。
年越し参拝のタイミング
年越し参拝のタイミングは、日付が変わる直前、日付が変わった直後、または元旦の早朝が一般的です。有名な神社は日付が変わる前後が非常に混雑するため、落ち着いて参拝したい場合は、少し時間をずらして早朝に行くのもおすすめです。
参拝後の過ごし方
参拝を終えたら、ぜひ神社ならではの楽しみを満喫しましょう。おみくじを引いて年の運勢を占ったり、お守りや絵馬を求めたりするのも良い思い出になります。また、多くの神社では露店が出ており、温かい甘酒や軽食を楽しむことができます。
二年参りにおすすめの神社
どこへ参拝に行くかは、個人の自由です。まずは地元の氏神様に感謝と祈願を伝えるのが本来の習慣とされていますが、明治神宮や伏見稲荷大社などの有名な
出典:「京都・伏見「伏見稲荷大社」の見どころ|歴史あるお稲荷さんの「千本鳥居」|THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)宿泊・観光に最適な京都駅徒歩2分のラグジュアリーホテル<公式>⧉」|keihanhotels-resorts.co.jp
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/sight/yamari-fushimi-yamashina/post_9.html
出典:「ご参拝の方へ|明治神宮⧉」|meijijingu.or.jp
https://www.meijijingu.or.jp/sanpai/2.php
神社も多くの参拝者で賑わいます。また、比較的人が少ない穴場スポットを探して、静かに参拝するのも良いでしょう。
ANAのJapan Travel Plannerでは、初詣におすすめの神社として、佐賀県の祐徳稲荷神社、北海道の札幌諏訪神社、山口県の山﨑八幡宮などが紹介されています。
- 札幌諏訪神社: 北海道札幌市東区北12条東1-1-10。色とりどりの花を浮かべた華やかな花手水が有名で、レースでできたお守りや限定の御朱印も人気です。
- 山﨑八幡宮: 山口県周南市宮の前1-9-10。月替わりで季節の花をデザインした御朱印があり、年の干支をあしらった御朱印帳も毎年発売されているとのこと。
- 祐徳稲荷神社: 佐賀県鹿島市。お正月の時期には参拝者であふれ、鮮やかな朱色の鳥居がかかる石段を登ると山頂の奥の院にたどり着きます。
これらの情報を参考に、特別な神社を訪れてみるのも良い経験になるでしょう。
二年参りに関するよくある質問(FAQ)
- Q1: 二年参りは、必ず二つの神社を参拝しないといけない?
- A1: 二年参りの定義としては「二つの神社を参拝する」または「大晦日の夜に参拝し、日付が変わってから再度参拝する」というものがありますが、調整さんの記事にもあるように、日付変更付近に一度だけ参拝を済ませることもあります。大切なのは、感謝と祈願の気持ちです。
- Q2: 年末に初詣に行っても良い?
- A2: はい、問題ありません。これを「年末詣」と呼びます。村松虚空蔵尊だよりによると、年末詣は年一年の感謝を伝えることが主な意味合いですが、新しい年のお願い事をしても問題ありません。むしろ初詣よりも空いていることが多く、落ち着いて参拝できるメリットがあります。
- Q3: 二年参りにおすすめの服装は?
- A3: 大晦日から元旦にかけての夜間は非常に冷え込みます。温かいコートやマフラー、手袋、帽子など、防寒対策をしっかりとした服装で参拝しましょう。足元も冷えるので、厚手の靴下や防水性のある靴がおすすめです。
- Q4: 二年参りのお賽銭はいくら?
- A4: お賽銭に決まった金額はありません。大切なのは、金額よりも心を込めることです。「ご縁がありますように」と5円玉を入れる人もいれば、それぞれの願い事に合わせて金額を決める人もいます。無理のない範囲で、心を込めてお納めください。
- Q5: 二年参りは、一人で行っても良い?
- A5: はい、全く問題ありません。一人で静かに自分と向き合い、年の感謝や祈願をしたいという人にとって、一人での二年参りは非常に有意義な時間となるでしょう。
- Q6: 二年参りでお願いすることは?
- A6: 二年参りは、一年の感謝と新しい年の祈願を同時に行う行事です。家内安全、健康祈願、商売繁盛、恋愛成就、学業成就など、個人の様々な願い事を祈願することができます。まずは過ぎ去る年への感謝を伝え、その上で新しい年への願い事をしましょう。
- Q7: 二年参りで注意することは?
- A7: 防寒対策の徹底、交通機関の運行状況確認、混雑時のマナー遵守が重要です。特に、年越しの神社は非常に混み合うため、周囲への配慮を忘れずに、安全に参拝しましょう。また、体調管理にも十分注意してください。
- Q8: 二年参りの御朱印はどこでいただける?
- A8: 多くの神社では、元旦から御朱印をいただけます。しかし、年越しの夜間は対応していない場合もあるため、事前に参拝予定の神社に確認することをおすすめします。御朱印所が混雑することもあるので、時間に余裕を持って行きましょう。
- Q9: 二年参りは、どんな人におすすめ?
- A9: 二年参りは、過ぎ去る年への感謝と、新しい年への祈願を同時に行いたい人、年越しを特別な方法で迎えたい人、日本の伝統文化を体験したい人におすすめです。また、初詣の混雑を避けたい人にも、早朝参拝などの形で適しています。
まとめ:二年参りで迎える、素晴らしい新年
この記事では、年越しに神社へ行く「二年参り」について、その意味、由来、ご利益、そして参拝マナーまでを詳しくご紹介しました。
- 二年参りは、大晦日から元旦にかけて神社を参拝し、過ぎた年への感謝と新しい年への祈願を行う行事です。
- その由来は、古くからの「年籠り」という習慣にあり、現代の初詣とは異なる深い意味を持ちます。
- 年末詣も合わせると、神様のパワーが強いとされる時期に参拝することで、家内安全や健康祈願など、様々なご利益を得られるとされています。
- 参拝時には、防寒対策を徹底し、鳥居での一礼、手水舎での清め、二礼二拍手一礼といった基本的なマナーを守ることが大切です。
年越しに神社を訪れる「二年参り」は、一年を締めくくり、新たな年を清々しい気持ちで迎えるための素晴らしい行事です。ぜひ、この記事で得た知識を活かし、心を込めて参拝し、素晴らしい新年を迎えてください。あなたの年が心身ともに健やかで、たくさんの幸運に恵まれる一年になることを心より祈願いたします。